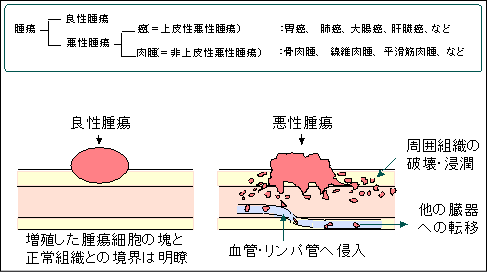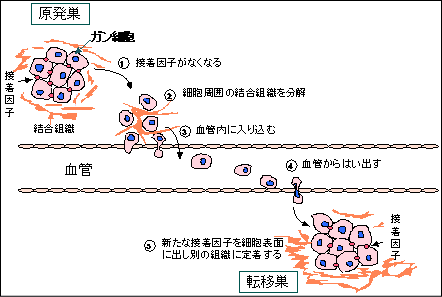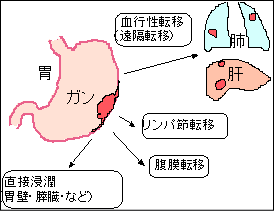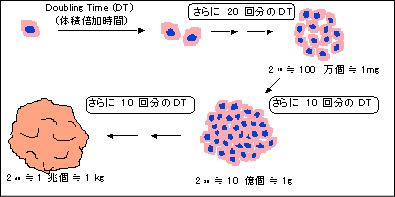第1章:医者まかせではがんの再発は防げない
2.がん再発の基礎知識
【がんの多くは転移する性質をもっている】
【転移と取り残しのがん細胞が増殖して再発する】
【がんの転移は大きくなるまで診断できない】
【手術で完全に切除したつもりでも再発することがある】
【がん組織の増大速度を遅くすれば再発を遅らせることができる】
【がんの多くは転移する性質をもっている】
私たちの体は約60兆個の細胞から成り立っています。それぞれの細胞の分裂や増殖は遺伝子の働きによって厳密にコントロールされており、自分勝手に増殖することはありません。しかし、ある種の遺伝子の働きに異常が起ると、必要もないのに勝手に増殖する細胞に変化することがあります。この異常な細胞によって作られた塊を「腫瘍」とよび、良性腫瘍と悪性腫瘍に区別されます。良性腫瘍は増殖が遅く局所的に細胞の塊を作るだけですが、悪性腫瘍は周囲の正常な細胞や組織をも破壊してしまう性質を持ち、さらに血液やリンパ液に乗って離れた臓器に飛んで行き、そこで新たな腫瘍を形成します。医学的には、粘膜上皮細胞や肝臓細胞など上皮系細胞から発生する悪性腫瘍を「癌(がん)」といい、筋肉・骨・軟骨・神経・線維芽細胞などの間質系細胞から発生する悪性腫瘍を「肉腫(にくしゅ)」と呼びますが、このサイトでは悪性腫瘍をまとめて「がん」と記載していきます(図2)。
図2:異常な細胞が増殖してできた細胞の塊を「腫瘍」という。良性腫瘍は限局性の細胞の塊を作るだけであるが、悪性腫瘍は腫瘍細胞が周囲の組織を破壊しながら広がり(浸潤性増殖という)、血管やリンパ管の中に入り込んで全身に転移する性質を持っている。
がんができた元の場所を原発巣といいます。がん細胞が原発巣だけに留まっているのであれば、たとえ大きな腫瘍であっても外科手術で完全に切り取ればがんを治すことができます。しかし、がん細胞は原発巣から離れた所へ飛んでいって、別の場所にもがん細胞の塊を形成しながら全身に広がる性質を持っています。これをがんの「転移」といいます。全ての組織には、栄養物や老廃物を運搬するためにリンパ液と血液が流れており、がん細胞はこのリンパ液や血液の流れに乗って、リンパ節や肝臓や肺など全身に運ばれ、新たながん組織(転移巣という)を形成するのです。
転移は行き当たりばったりでなく、背後には巧妙な仕組みがあります。同じ細胞が集まって組織を作るために、それぞれの細胞の表面にはお互いをつなぎ止めるための接着因子があります。がんになるとこの接着因子が異常を起こして機能しなくなったり消失したりしてバラバラになりやすくなるのです。さらに蛋白質分解酵素を分泌して周囲の結合組織や血管壁を破壊しながらさらに突き進み、別の臓器や組織に定着して増殖を開始します(図3)。従って、がん細胞が転移するためには、がん細胞同士が離れやすくなること、まわりの結合組織を分解しながら活発に運動すること、死ににくくなることなどの条件が必要で、細胞の増殖や接着や死(アポトーシス)に関連する遺伝子(がん遺伝子やがん抑制遺伝子)の異常が多数蓄積して、悪性化がより進んだがん細胞ほど転移しやすい傾向にあります。
良性腫瘍はその部分を切り取れば完全に治ります。がんも転移する前に完全に腫瘍を切り取れば治るのですが、がんは診断された時点、つまり目にみえるほど大きくなった時点ではすでに他の場所に転移していることが多いため、再発する宿命を持っているのです。
図3:がん転移のメカニズム。がん細胞は接着因子の異常あるいは消失により原発巣から離れ、 結合織の分解して血管内へ侵入して他の組織や臓器に運ばれる。さらに血管外にはい出して、新たに接着因子を合成して離れた組織に定着して転移巣をつくる【転移と取り残しのがん細胞が増殖して再発する】
がん細胞は、結合組織を分解しながら活発に移動する性質をもっており、周囲組織に広がっていきます。これをがんの浸潤性増殖といいます。がんの手術では、目で見えるがん組織からできるだけ離れた正常組織まで含めて切除することが基本ですが、それは目に見えないところまでがん細胞が広がっているため、取り残すと原発部位から再びがんが増殖してくるからです。これを局所再発といいます。例えば、増殖が速く浸潤性が強いがんでは、肉眼的に認められるがんの端から5cm離しても、切除断端にがん細胞を認めることがあります。このようにがんを取り残すと局所再発が起こってきます。
がんはリンパの流れにのって周囲のリンパ節に転移していることが多く、そのためがんの手術では周囲のリンパ節も一緒に切除します(リンパ節廓清という)。がん細胞が血液に乗って遠くの組織や臓器に転移している場合には、全身に散らばっているがん細胞を殺すために抗がん剤の投与が行われます。がんの外科手術後の再発というのは、がん組織を切除した局所に取り残しがあった場合と、すでにがんが他の臓器やリンパ節などに転移していた場合に、残ったがん細胞が増殖して起こります(図4)。
がんがどこかに残った場合、次第に増殖して多くは5年以内にそのほとんどが発症してしまいます。治療の効果を比べるために5年生存率(その治療を受けた人の何パーセントが5年後に生存しているかを表わす率)が使われたり、「がんは手術して5年経てば治った」という話を聞くのは、手術後5年後以降に再発することは稀であるからです。
しかし、手術の後に補助療法(抗がん剤や放射線による治療)を追加して、再発や転移があっても5年以上生き延びることも珍しくありませんし、増殖の遅いがんでは10年以上してから再発するものもあります。
図4:胃がんを例にとってがんが広がるルートを示している
胃にできたがん細胞は胃壁に沿って浸潤性に増殖し、膵臓や腹膜など隣接した組織にも広がっていく。リンパ管に入ると周囲のリンパ節に転移し、血管に入ると肝臓や肺など離れた臓器に転移する。手術で原発巣を切除しても、がんの取り残しや、離れた臓器に転移(遠隔転移)があると再発する。【がんの転移は大きくなるまで診断できない】
転移したての小さな転移巣は、どんな診断方法を用いても捉えられませんし、当然、手術で取り去ることも不可能です。転移巣のがん細胞が増殖し、目に見える大きさまで数が増えた時に初めてがんの転移が診断できるのですが、その時には既に数億個以上のがん細胞がいることになります。1グラムのがん組織で約10億個のがん細胞がいます。
全身にばら撒かれえるというがん転移の性質上、もし一個の転移巣が見つかれば、目に見えないレベルの転移巣は他の部位にも存在すると考えるべきです。例えば、大腸がんの手術後1年たって、CTや超音波検査で肝臓に転移巣が一個見つかったとき、「がんの転移が肝臓に一箇所見つかりました」としか医者は言えません。目に見えなければ他の部位にも転移がある確証は100%ではないわけですから、この説明は間違いではありません。しかし、実際は「目に見える転移巣が肝臓に一箇所あるから、目に見えないレベルの微小な転移巣が複数(場合によっては無数)あるはずです」というのが常識的な解釈です。このような患者さんの肝臓を病理組織学的に丁寧に調べると、顕微鏡でしか見つからないレベルの小さながん転移巣が多数見つかることが多いからです。
大腸がんの肝臓転移では、目に見える転移が少数であれば転移巣を切除するほうがより長く生存できることが報告されています。目に見えないがん転移巣が肝臓全体に広がっている可能性は高いのですが、大きな転移巣を取り去ったあとに、残った目に見えないがん細胞を抗がん剤などで増殖を抑制すれば、がんで死亡するまでの時間稼ぎができるからです。残ったがん細胞が少なければ、免疫力や自然治癒力を高めてやるだけでがんの増殖を押さえ込むことも可能です。【手術で完全に切除したつもりでも再発することがある】
治療後にがんが再発してくる確率は、がんの種類(発生臓器)や進み具合(ステージ)によって異なります。がんを切除したあとに、がん細胞の性質(悪性度)や広がり、リンパ節への転移の有無などを顕微鏡で検査すると転移や局所再発の可能性を推測することができます。がんが大きかったり、リンパ節に転移が見つかったりすると、たとえ目で見える転移がなくても、体のどこかにがん細胞が残っている可能性があるので、手術後に抗がん剤や放射線療法によって残存しているかもしれないがん細胞を叩いて再発を予防します。
がん組織が限局していてがんから十分な距離をおいて切除し、リンパ節転移や他の臓器への転移も見つからなかった場合、その手術は治癒切除といいます。がんを根こそぎ切除して、体に残っているがん細胞は居ないと考えるわけですから、治癒切除の場合は理論的にはがんの再発は起こらないはずです。しかし、このような治癒切除でも10〜20%は5年以内に再発しているという事実があります。その理由は、たとえ原発巣が小さくても肉眼的に見える大きさになったがんは既に転移している可能性があることと、目にみえない小さながん転移は診断できないからです。
大雑把にいって、直径1cmのがん組織(約0.5グラム)には約5億個のがん細胞が、米粒大の大きさで1000万から2000万個のがん細胞がいます。手術中に目で見えるところに米粒大のがん転移があれば見つけることができるかもしれません。しかし、その十分の1の大きさになると肉眼的な診断は困難です。肝臓の中に転移巣がある場合には直径が1cm以上でもみつかりません。臓器の中にある場合には、CTやエコーで検査すれば転移巣を検出することができますが、この場合には1cmくらいに大きくなっていないと検出は困難です。つまり、がん細胞が数億個に増えるまでは多くの場合、体の外からがんの転移を検出することは困難なのです。【がん組織の増大速度を遅くすれば再発を遅らせることができる】
腫瘍の体積が2倍になる時間を体積倍加時間(Doubling Time, DT)といっています。一個のがん細胞が30回分のTDを経て約10億個(≒2の30乗)のがん細胞からなる約1グラムのがん組織に成長し、さらにもう10回分のDTを経ると1kgのがん組織になる計算です(図5)。
図5:がんの体積倍加時間(doubling time)
がん組織の体積が2倍になる時間を体積倍加時間(DT)という。1個のがん細胞が20回分のDTで1ミリグラム(約100万個)のがんになるが、この時点ではがん組織は目に見えない。さらに10回分のDTを経て1グラムのがん組織になって診断できるようになる。さらに10回分のDTで1キログラムのがん組織になるとがん死する。
固形がん(胃がんや肺がんのように塊をつくるがん)の体積倍加時間(DT)は通常は数十日から数百日のレベルと言われています。例えば、早期大腸がんの多くはDTが18〜58ヶ月の間でその平均が26ヶ月という報告や、肺がんの平均DTが166日という報告がなされています。しかし、転移するようながん細胞は悪性度が増して増殖速度も早いのでDTはもっと短くなっています。
がん転移は、最初は1個のがん細胞から始まって次第に数が増えていきます。がん細胞の増殖速度が早ければがん組織のDTは短くなりますが、細胞の増殖速度を遅くしたり、免疫細胞ががん細胞を殺す力を高めたり、血流を阻害してがん組織に栄養が十分行かないようにすれば、そのがん組織のDTを長くする事ができます。
DTが1ヶ月のがん細胞が一個残っていると40ヶ月で約1kgの大きさに成長してしまいますが、DTを2倍にすれば1kgになるのに80ヶ月かかることになります。つまり、DTを2倍に伸ばすことができれば、手術後の生存期間を2倍に伸ばすことができます。たとえがん細胞を完全に殺すことができなくても、がん組織の増大速度を遅くするような方法をとれば、がんと共存しながら延命することが可能となるのです。がん組織のDTを少しでも長くする方法を幾つも併用すれば、もっと長く再発を遅らせることができます。このサイトでこれから述べていく方法の多くはがん組織のDTを伸ばす効果が期待できるものであり、それらを多く実行すればより長くがんの再発を予防することが可能となるのです。
目次へ戻る ホームへ戻る 2章-1へ